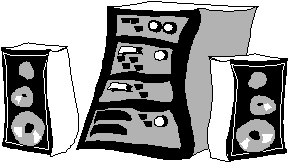| |
| トップ | この記事へのコメント | サイトマップ | コンタクト | ログイン | |
| ホンの基礎知識 | |||
| 1. マルチアンプの基礎知識 2. デジタル技術の基礎知識 3. FAQ-むだづかいにNO! | |||
| <他のセクション> | |||
| |||
| - ホンの基礎知識 - |
| デジタル技術の基礎知識 |
 | |
このページは、オーディオファンを悩ませるデジタル技術についてその概要を少しだけ説明するものです。「知っているよ」という人は読み飛ばしてください。
「デジタル」という言葉は一部のオーディオファンにとって謎の存在です。また、一部のマニアは、ことにアナログオーディオ時代に技術を高めたマニアは、それを悪魔の呪文のように警戒するようです。分かりにくい部分があるのは確かですが、悪魔の呪文とはどういうことでしょう。
このページはその謎の正体を説明し、呪文を無効化します。もう「デジタル」と聞いただけで身構える必要はありません。デジタルオーディオはアナログオーディオと同じ目標を持っています。便利なやり方が発見されただけなのです。
| アナログとデジタル | ホンの基礎知識 - デジタル技術の基礎知識 | |
アナログとデジタルのもともとの言葉の意味は他の場所で調べてください。ここでは、オーディオにおけるアナログとデジタルについて説明します。あなたがオーディオの世界で「アナログ」または「デジタル」という用語を使うとき、それをどんな意味で使っていますか? 「連続的」や「離散的」では説明不十分ですよね。「音はアナログ」、「PC内部はデジタル」も不十分です。
製品レベルの話にして、たとえばアナログアンプとデジタルアンプの区別はどうすればいいですか? チャンネルデバイダーでアナログ製品とデジタル製品はどうちがいますか? LPレコードはアナログでCDはデジタルということはみんなが知っていますが、何を理由にして区別しているのでしょう。そもそも、なぜそんな区別をするのでしょう。区別しなければならない理由は何でしょう。区別することにどんなメリットがあるのでしょう。
| アナログだと困ったことになる | |||
自然界の音や楽器の音などすべての音は空気の粗密波です。音は、空気が粗の状態(圧力の低い状態)から密の状態(圧力の高い状態)へ、密の状態から粗の状態へと連続的に変化したものです。空気の密度が連続的に変化するとき、人はそれを音として認識します。このように、途切れなく連続して変化する情報を数量として取り扱うこと、またはそのやり方を「アナログ」と呼びます。つまり、音はアナログのデータです。
オーディオ技術の初期の段階では、マイクロフォン等で採取したアナログデータは、電気信号に変換され、それを何かの記憶媒体(メディア)にアナログのまま保存されました。たとえば磁気テープなどに保存され、そこからLPレコードなどが作成されました。そしてアナログオーディオの文化が大きく花開きました。音楽ファンはコンサート会場に行く必要がなくなったのです。グレン・グールドの予言通りです。
| |||
しかし、しばらくするとオーディオファンは困ったことに気付きました。
- LPレコードも磁気テープも経年により音が劣化してしまう。
- アナログデータをコピー(ダビング)すると、コピーのたびに音が劣化してしまう。
- アナログデータを圧縮すると音が悪くなり、元にもどすこともできない。
- LPレコード片面に入らない楽曲がある。プレーヤーを一時停止し、レコードを反転させなければならない。
- テープレコーダーを長時間モードで使う場合、音質を犠牲にしなければならない。
- 生演奏の広いダイナミックレンジを再現できない。
これらの問題の多くは、音源データがアナログであることが原因です。アナログデータは、その最初の状態を維持することが難しく、環境からの悪影響を受けやすいのです。LPレコードの製作現場では高性能の機材を使ってマスターディスクが作成されましたが、それでもやはり劣化は時間の問題でした。
| 分からないように捨ててしまおう | |||
オーディオにおけるアナログデータの主な問題点は、(1) データのサイズが大きくなる、(2) 当初の音質を維持できない、の2点です。そこでオーディオ技術者が考えたのが、「アナログデータを間引きし、音の情報を固定しよう」ということでした。間引きすれば全体のサイズを小さくでき、情報を固定すれば劣化がなくなり、コピー等も可能になるというわけです。でも、どうやって?
音声や画像のアナログデータは、わずかであればその内容を変化させてもそれを人の耳や目で判別するのは難しいという特徴があります。そこで、それと分からない微細さでデータを捨ててしまおうというのがオーディオにおける間引きの発想です。たとえば、ある音声がどんなものであるかは、それをずっと聞き続けている必要はなく、短いタイミングで飛び飛びに聞いていても分かるということです。非常に短いタイミングで聞けば、実際には寸断されている音でも人の耳には完全に連続した音として、つまりアナログ音声と変わらないものとして聞こえることになります。
| |||
そこで利用されたのがデジタル技術です。間引きしながら得られたデータをデジタルデータとして数値で管理することにしたのです。たとえば、アナログデータを1秒間に44,100回という短いタイミングで次々に現在の音量をチェックし、得られた個々のデータを16桁の2進数(16ビット)で記録することにすれば、それはCD規格のデジタルデータになります。CDでは16ビットで表される音量データが1秒間に44,100回再生されるということですが、これを16bit/44.1kHzのデジタルデータと表記することがあります。
間引きして飛び飛びにデータを取り出すことをサンプリング(標本化)と呼び、サンプリングの頻度をサンプル周波数(サンプリング周波数) と呼びます。また、個々のデータを数値として記述する場合の2進数の桁数(ビット数)をビット深度と呼びます。ビット深度は、量子化ビット数、ビット長、ワード長、語長などとも呼ばれます。
くどいですが、たとえば16bit/44.1kHzと示されたデジタル音源データは、オリジナルのデータを1秒間に44,100回サンプリングして取り出し、個々の音量データを16ビットの数値で記録したものです。サンプリングされない残りのデータはみんな捨てているということです。
アナログデータをデジタルデータに変換することをアナログ・デジタル変換やAD変換と呼びます。変換を行う回路や装置がADCです。ビット深度が深いほど、サンプル周波数が高いほど、そのデジタルデータはオリジナルデータに近くなりますが、データサイズが大きくなり、プロセッサの性能も要求されるという問題があります。人間の聴覚能力を考えれば、24bit/96kHz程度で十分ではないかと小庵は考えています。ただし、放送局などはさらに高精度のデータを持っています。
実際、オーディオ用デジタルデータの大部分はPCMフォーマットだ。
しかし、2000年ころに登場したDSDフォーマットは異なる方法で音の管理を行う。SACDはDSDフォーマットのオーディオデータを暗号化して格納している。インターネットの楽曲配信サービスからは暗号化されていないDSDデータを入手できる。
DSDの場合はビット深度が "1bit" でサンプル周波数が "2.8MHz" などになっている。PCMとは大きく変わっているね。DSDの考え方は「音の粗密の状態を "1" か "0" で表現し、サンプリングを極めて高速に行うことで音源情報をできるだけ忠実に再現する」ということだ。サンプル周波数で言えばCD規格の少なくとも64倍になる。
DSD音源はアナログ音源に近い音質が期待できるという評価があるが、SACDについては、そこからのリッピングが法律で禁止されてしまったことで国内では普及が進まないようだ。開発の当事者であるソニー社やフィリップス社自身が製品の販売に熱心でないし、「SACDはもう終わった」と言う声もある。オーディオファンにとって残念なことだ。
| それで? | |||
なんで2進数なの?
それはデジタルデータがコンピュータまたは同等の機器で扱われるからです。コンピュータは歴史的に2進数を扱います。2進数でなくてもかまわないのですが、電子機器の決定的な特徴、つまりそれは電気を利用する機械であり、電圧がかかっているか、かかっていないかの2つの状態しか基本的に持たないので、それぞれの状態を "1" と "0" で表現することにしてデータ処理を行えば、何をするにもシンプルかつ便利だということになったのです。これを2進法と言います。2進法で書いた数値が2進数です。人間が使っている10進法は2進法よりずっと複雑な記数法なのですが、あなたはそれを知っていましたか? PCの前で自慢してやりましょう。
なんで16ビットなの?
|
なんで44.1kHzなの?
それは、「CDはそれくらいでちょうどいいだろう」とソニー社やフィリップス社の技術者が考えたからです。サンプル周波数を高くすれば高精度のデジタルデータになりますが、データ量が多くなってCDメディアに入れられる楽曲の数を減らさなければなりません。一方で低くすればアナログの音に負けてしまいます。人間の可聴周波数が20Hz-20,000Hzであることも考える必要があります。20,000Hzの音をデジタルシステムで正しく再生するためには、理論上は1秒間に40,000回以上のサンプリングを行う必要があります(標本化定理)。それらの事情を総合した結果、44,100Hz(44.1kHz)になったということです。なお、"44,100" という不可解な数値になったのには理由があり、(1) デジタル機器は内部動作のためにタイミングを取る必要があり、(2) そのために時計のような内部機構が必要で、(3) ちょうど水晶が通電に反応して高精度の発振を行うことが分かっていたので、それで水晶の発振周波数をもとにして "44,100" になったというわけです。水晶は人間の都合なんか知りませんからね。
音の高さの情報はどこへ行った?
ビット深度が音の大きさを表すのなら、「音の高さの情報はどこへ行ったの?」と思いませんか。「旋律の情報がないと楽曲にならないのでは?」ということですね。
宿題にしたらどうだ。
ビーフジャーキーをリクエストします。
| デジタル技術の長所と短所 | ホンの基礎知識 - デジタル技術の基礎知識 | |
もう分かったと思いますが、オーディオをデジタル技術で楽しむことには以下のメリットがあります。
| 楽曲管理上のメリット | |||
音が劣化(変化)しない。
これは最大のメリットです。オーディオ分野に限りませんが、デジタルデータは、もしそこに内容の変化(エラー)が起きた場合、それを簡単にチェックすることができます。CDに書き込んでも、ファイルに保存しても、それらを何度繰り返しても、デジタルデータはほとんど完全にオリジナルの品質を保つことができます。データが変化しないということは、音の劣化がないということです。もっとも、アナログデータをデジタルに変換すること自体を劣化と考えることもできるので、正確に言えば「最初にちょっと劣化させて作ったデジタル音源は決してそれ以上は劣化しない」ということになります。
たとえば周波数特性やダイナミックレンジが変化し、位相回転やクロストークが起こる。多かれ少なかれノイズも混入する。原音再生という観点から見ると、これらのすべては音の劣化と言える。高性能・高価格の機器を使っても例外はない。
完全にコピーできる。
これはみんなが知っていますよね。デジタルデータはとても簡単にコピーを作ることができます。オリジナルとコピーとが完全に同じかどうかをチェックすることもできます。でも、どうやって? なお、SACD上の楽曲データのようにコピー不可(リッピング不可)と言われるものもありますが、「コピーはできるが法律で禁止されている」と言うのが正確です。
安価な多種のメディアに記録できる。
デジタル化した音源データは、何なら曲の全体を紙に手書きすることができます。CDやDVDに焼くことができ、USBメモリやハードディスクに保存することができ、省スペースで長く保存することができます。32GB容量のUSBメモリは1,000円ほどで購入できますが、3分強ほどのPOPs楽曲をCD品質のデータ(16bit/44.1kHz)でそこに保存するなら、200万曲を超える収録が可能です。
データを圧縮できる。
データの種類にもよりますが、楽曲データは特別な方法でデータサイズを小さくすることができます。デジタルデータは1と0が延々と並びますが、たとえば1が100個も並ぶ場合、それをそのまま書くより「1が100個」と記録する方がデータ量が少なくなりますね。このようにデータを再構成してサイズを小さくすることを「圧縮」と呼びます。データを圧縮すれば限られたメモリを有効活用でき、またデータ伝送も短時間で完了します。オリジナルデータを再現できる圧縮方法を「可逆圧縮」と呼び、そうでないものを「不可逆圧縮」と呼びます。高品質で楽曲再生を行いたい場合は可逆圧縮を利用します。もちろん、楽曲を再生するときは圧縮されたデータを元に戻すことになります。(説明は実装技術そのままではありません)
長距離伝送でも問題がない。
デジタルデータはエラーなしで遠方へ送り届けることができます。実例がインターネットのストリーミングサービスです。この場合、たとえばデジタルデータが太平洋を渡ることもありますが、ちゃんと楽曲は再生されますよね。長距離というほどではありませんが、小庵は3組のマルチアンプシステムのそれぞれに劣化のない楽曲データを届けるためにデジタル機器を使用し、たとえば合計12mの光ケーブルで接続していますが、再生音には何の影響もありません。アナログ伝送でそんなことをすれば怒られます。
データを正確に編集・加工・調整できる。
デジタルデータは、もしお望みならそれを編集したり加工することが容易です。デジタルチャンネルデバイダーもその特徴を利用しています。デジタルシステムの場合、アナログシステムよりも格段の精度で、しかも容易にそれらを実行できるのです。編集・加工の一例ですが、レコーディングスタジオでは、録音したデジタルデータを必要に応じて自由に編集しています。たとえば、ピアニストがミスタッチをしても、ボーカルが半音ずらしても、それをデータ上で修正して完璧な演奏に仕立てることができます。ランチに行ったアーティストを呼び戻して再演してもらう必要はありません。
ダイナミックレンジの広い楽曲を鑑賞できる。
演奏者の腕前や楽器の性能にもよりますが、生演奏は最小音から最大音までの幅が大きく、そのダイナミックレンジが100dBを超えることもあるそうです。100dBはLPレコードや磁気テープなどのアナログメディアでは記録できず再生も不可能です。最大音をひずみなく再生できるようにすると最小音がノイズの中に埋もれてしまい、最小音をちゃんと聞き取れるようにすると、最大音がひずんでしまうのです。LPレコードのダイナミックレンジは60dB程度と言われます。CDの場合、16ビットの音量表現なので96dBのダイナミックレンジを実現することができます(1ビットが6dBに相当)。しかし、CDでも100dBの熱演は再現できませんね。そこでビット深度をたとえば24ビットや32ビットにしようというのが近年のハイレゾオーディオブームの動機の一つになっています。
マルチチャンネル音源への道が開けた。
あなたは5.1chや7.1chのマルチチャンネル音源を楽しんだことはありますか? 2chステレオにはない圧倒的な音場がありますよね。アナログオーディオ時代も2chステレオを超えるマルチチャンネル音源の試みはありましたが、2ch以外のチャンネルは擬似音源で、現代の5.1chや7.1chのように演奏者をサラウンドチャンネルに配置したりバイクを360度走らせるというようなことはできませんでした。デジタル技術では、サンプリングしたデータ(16ビットや24ビットのサンプル)の一つ一つを、「これはフロント左チャンネルの音」、「これはサラウンド右チャンネルの音」などと区別して管理することができます。そのようにしてDVDやSACDは6チャンネルの音源に、Blu-rayディスクは8チャンネルの音源に対応しています。
| 音響機器へのメリット | |||
デジタル技術はオーディオ機器にも大きな貢献をしました。
高性能の関連機器を安価に製造できるようになった。
アナログ機器は、オーディオ信号が通過する回路にある抵抗器やコンデンサーなどが音質に影響を与えることがあるので、メーカーやマニアの一部はオーディオグレードと呼ばれる高品質のものを使うことがありました。電源の品質も再生音に影響がありました。当然、高品質を目指せば特別なコストがかかってしまいますね。でも、デジタル回路は "0" と "1" を判別できれば完全な処理ができるように作られているので、演算用チップを除けば高性能部品を必要とせず、電源も簡略化できます。このため、デジタル製品の多くは驚くほどの低価格で製造・販売できるようになりました。
外来要因による悪影響を防げるようになった。
外来要因とは、LPレコードプレーヤーのモーター音、床やオーディオラックの振動、アンプ内で発生するノイズ、エアコンなど電気製品からのノイズ、受電設備からのノイズ、放送電波の影響などです。アナログオーディオではこれらを原因とするノイズや音質の劣化に注意を払う必要がありました。問題の解消のためには多くの試行錯誤と投資が必要だったのです。
でも、極端な場合を除いてデジタル機器はこれらの影響を受けません。たとえば、PCは典型的なデジタル製品ですが、貧弱なスイッチング電源なのに高度なデジタル処理に何の不都合もありません。PC内蔵のCDドライブは回転ムラがひどいですが、リッピングへの影響はなく再生音にも影響はありません。PCの冷却ファンががたついて騒音や振動があっても、マザーボードをむき出しにして冷蔵庫の近くに置いても、スピーカーマグネットをそこに近づけても、マウスやキーボードを振り回しても、何のエラーも起きないはずです。
音場を手軽に管理できるようになった。
魅力的なオーディオ空間を構築するためには、スピーカーから出てくる音の位相やタイムアラインメントを正確に管理する必要があります。測定機を持たないとこれは2chステレオでも難しい作業で、近年の5.1chや7.1chのマルチチャンネル音源になるとほとんど不可能です。でも、音源をデジタルデータで管理できるようになったため、DSPと呼ばれるプロセッサとマイクロフォンを使えば容易にその難関を突破することができます。近年の大部分のAVアンプはDSPを持っているはずです。デジタルチャンネルデバイダーはDSPや同等の回路で周波数帯分割などのフィルタ処理を行っています。
低電圧・低電力で運用できるようになった。
真空管アンプは数百ボルトの電源を必要とします。アナログ半導体アンプは電圧は数十ボルトですが電流量は多くなります。どちらも大電力を消費します。デジタル機器はそうではありません。PCの回路の大部分は5Vまたは12Vの電源で動作しています。USB DACは5Vで動作します。消費電流もアナログ機器よりずっと少なくなっています。
| デメリットもあります | |||
一方で、オーディオにおけるデジタル技術と関連製品には以下のような問題があります。
間引きすることがそもそも問題。
サンプリングにおいて、ビット深度を浅くしたりサンプル周波数を低くすれば、聞くに堪えない音になります。なめらかな音量管理はできず、ダイナミックレンジも狭くなります。「平べったいカクカクした再生音」になり、音量を絞った再生ではバイオリンの音なのかフルートの音なのかを区別できなくなることがあります。音の情報が大きく間引きされることが原因です。アナログシステムではこのようなことは起きません。アンチ・デジタル派はこの点を強く批判します。根本的に致命的だというのです。
コピーできることが問題。
「デジタルデータは完全にコピーできる」という事実は多くの人々に大きなメリットがある一方、たとえば楽曲の作者やその著作権団体には大きな脅威になります。かつてCDによる楽曲販売は世界的な成功を収めましたが、容易にそのコピーを作ることができたため、実際にはCDを購入せずに楽曲データを手に入れた多くの人々がいたと言われます。これは著作権者やCD販売者が正当な収入を失ったことを意味します。許されることではありませんね。問題を放置すれば音楽文化そのものに悪影響があるかもしれません。
遅延があります。
デジタル機器は、内蔵するプロセッサで種々の演算(広い意味の計算)を行っていますが、そのさいデータのやり取りやメモリへの書き込み、読み出しなどで処理のタイミングを合わせる必要があります。タイミングが合わない場合、合うまで待つことになります。非常に短い待ち時間ですが、何度も同じ状況になることもあります。デジタルチャンネルデバイダーではフィルタの減衰カーブを急峻にしようとすれば同じ演算を何度も繰り返すことになるので、遅延時間が増えることになります。デジタル機器は基本的にそのようなことが起きる機械だと思ってください。つまり、必ず遅延が起きます。どのような遅延になるかは機器の設計や演算内容によります。良心的なデジタル機器は、それを使うことでどれほどの遅延が起きるか仕様書に書いています。多くはミリ秒単位です。アナログ機器ではほとんど遅延はないので、たとえばあなたのオーディオシステムでアナログ機器とデジタル機器を混在させる場合、構成によっては遅延対策を検討しなければならないことがあります。
故障への自力対応は困難です。
アナログ機器の場合、多少の経験と知識があればケースを開けて回路をたどり故障箇所を見つけて修理することが可能です。真空管アンプ時代には多くのマニアが実際にそうしていました。しかし、デジタル機器はそれは容易ではありません。高度な技術力が必要です。もっとも、機器はとても安価なので「悩むくらいなら買い換えよう」という判断が今流です。
家具のような外観デザインではありません。
オーディオ機器に家具としての価値も求める人にとってデジタル機器の大部分はまったく魅力がありません。居間にも置かれることがあるということを機器メーカーが考慮していないのです。それだからこそ安価なのですが。
家庭内オーディオで使いにくいものがあります。
デジタル機器の中には家庭内オーディオで使うことを考慮していないものがあります。(1) 電源のオン・オフ時にポップノイズが出る、(2) 大きな入力信号電圧を必要とする、(3) コネクタが一般的でない、(4) 専用ラックでの運用を前提にしている、などです。
| デジタル技術に親しもう | ホンの基礎知識 - デジタル技術の基礎知識 | |
| 音の高さの情報はどこへ行った? | |||
CDには16bit/44.1kHzのデジタルデータが記録されていることは前に書いた通りです。でも個々の16ビットのデータは音量のデータなのですよね。それが集まっているだけです。ディスクの管理情報を除き、そのほかにはCDにはデータはありません。すると、音の高さのデータはどこへ行ったのでしょうか。音の高さの変化を楽しむのが音楽なのです。
16ビットのデジタルデータがアナログデータに変換されてスピーカーから次々に空中に再生されるとき、そこに空気圧の変化が生まれます。スピーカーの振動板(ダイヤフラム)がユニットの前方に動けば、そこには空気圧の高い場所ができ、それが後退するときには空気圧の低い場所がそこにできます。そのでき方はデータ内容に応じたものになります。その空気圧の変化を人は音の高さとして感じます。空気圧の高い場所がどんな頻度でやってくるかを人は判別しているということです。
つまり、音の高さの情報はCDのどこにも記録されていないものの、ビット深度やサンプル周波数に従ってスピーカーが動作すれば、そこに音の高さが再現されるということです。
| ADC、DAC、DDCのこと | |||
オーディオ雑誌やインターネットのオーディオ関連サイトで見かける用語のうち、ADC、DAC、DDCについて説明します。
ADCについて
アナログ・デジタル・コンバーターで、アナログデータをデジタルデータに変換するソフトウェアまたはハードウェアです。変換はとくに高度な技術を必要としないので2,000円程度から市販品を入手できますが、ビット深度を深くするほど、サンプル周波数を高くするほどプロセッサの能力を高くする必要があるので、そのぶん高価になります。
DACについて
デジタル・アナログ・コンバーターで、デジタルデータをアナログデータに変換するソフトウェアまたはハードウェアです。購入するときはビット深度やサンプル周波数に注目し、あなたの要求に合ったものを選びましよう。安価な製品は2,000円程度から入手できます。数十万円以上のものもありますが、価格を正当化する根拠があるのか小庵は疑問に思っています。
DDCについて
デジタル・デジタル・コンバーターで、デジタルデータのフォーマットやビット深度、サンプル周波数を変換するソフトウェアまたはハードウェアです。デジタルオーディオに深入りするようになれば必ずお世話になります。安価なはずです。
| デジタルケーブルについて | |||
デジタルオーディオを楽しむにはアナログオーディオでは見なかったケーブルが必要になります。
|
AES/EBUケーブル
デジタル機器間を接続するときに使います。1本のケーブルで2chステレオ信号を伝送できます。XLRケーブルと外観は同じです。
HDMIケーブル
映像や音声などのデジタル信号を広帯域で伝送できるケーブルです。7.1chのマルチチャンネル音源に対応します。
LANケーブル
コンピュータネットワークで利用されるケーブルです。丸いもの、フラットなものがカラフルに用意されています。カテゴリバージョンの大きいものほど広帯域伝送が可能ですが、中継機器(ハブやルータ)等もそれに対応している必要があります。
USBケーブル
USBデバイスのための接続ケーブルです。PCユーザは日常的に使っていますよね。オーディオではDAC等への接続で使います。2020年の時点で最新規格はUSB 3.0です。バージョンの高いものほど広帯域伝送が可能です。
XLRケーブル
平衡型と呼ばれる3ピンのコネクタを持つ接続ケーブルで、アナログ機器の接続にも使われます。小庵のチャレンジではデジタルチャンネルデバイダーや関連機器の接続で何本も使います。
光ケーブル(TOS-Link、光ファイバーケーブル)
光信号を伝送するケーブルです。CD/DVDプレーヤーやテレビなど、多くのデジタル機器で使われています。5.1chまでのマルチチャンネル音源を伝送できます。
同軸ケーブル (コアキシャルケーブル)
銅線の伝送ケーブルで、銅の芯線を網目状のシールド線が丸く包む構造になっています。5.1chまでのマルチチャンネル音源を伝送できます。アナログ機器の接続にも使われます。
これらのケーブルをあなたが購入する場合、規格やバージョンに従った適切な選択をする必要があります。規格等を満たしているなら安価なものでも100%の性能を期待できます。「オーディオ用」と書いてあるものを選ぶ必要はありません。ただし、ひんぱんにケーブルの抜き差しをする環境のためにはコネクタ等がしっかり作ってあるものを選びましょう。
| 「広帯域」と「高速」 | |||
デジタルケーブルの説明で「広帯域」という用語を使いましたが、これは「高速」という意味ではありません。
「広帯域」とは、「より多くのデータを送受できる」という意味で、「個々のデータをより高速に送受できる」という意味ではありません。銅線や光ファイバーを流れる電子や光子の運動速度は一定(光速)です。これは太い線でも細い線でも変わりません。一方、単位時間にどれだけのデータを送受できるかはメディアの特性や伝送方法によります。たとえばパルス信号でデータを送信する場合、パルスの送信間隔を短くすれば単位時間あたりの送信データ量を増やすことができます。これが広帯域になるということで、パルス信号そのものの伝送速度が速くなるわけではありません。ただし、広帯域化は、採用したメディアや制御用ソフトウェアが実際にそのような伝送に対応できる必要があります。
個々のデータの移動速度は変わらないものの、単位時間に送受できるデータの量がメディアや伝送方法によって変わるということです。広帯域であればあるほど、結果として短時間に伝送が完了するので、それは感覚的には高速になったことと同じなのですが。
| デジタルオーディオのワンポイント | ホンの基礎知識 - デジタル技術の基礎知識 | |
本サイトではチャンネルデバイダー等にデジタル機器を利用するマルチアンプシステムについて書いていますが、それらは安価な機器であっても使い方一つで優れた性能を発揮してくれる一方、不注意な使い方をすれば高級機でも期待通りの性能を発揮できないという問題点を持っていることに注意が必要です。
でも、最も重要なポイントは以下のようにとてもシンプルです。
| アナログ信号をデジタル機器に入力する場合は注意が必要です。 | |||
この問題は、アナログ信号をデジタル機器に入力するときに発生する問題なので、たとえばあなたがCD等からデジタル出力をそのままチャンネルデバイダー等に入力している場合は以降の説明を読む必要はありません。CD等のデジタルメディアではデジタル機器のための音量管理がすでに行われているからです。
オーディオ用デジタル機器は入力されたアナログ信号を既定の周波数でサンプリングし、たとえば16ビットのデジタルデータに変換します。前記のように個々のデータは音量ステップを表すデータです。もし16ビットすべてをうまく使えるようにデジタル変換を実行できるなら、それは最大65,536段階で音量を管理できることを意味します。
|
ですから、デジタル機器にアナログ入力を行う場合、楽曲のピーク音量が16ビットの最大値になるように入力信号の大きさを調整する必要があります。さもないとデジタル変換後のデータが16ビットを使い切れないことになり、音量管理がなめらかにならず、弱音は痩せた音になり、強音は力感のないものになります。
デジタル機器が期待する十分な信号電圧でアナログ入力を行う必要があるということです。
| ゼロデシベル(最大音量)でデジタル機器に入力しましょう。 | |||
デジタル機器が期待する最大信号電圧が何ボルト(またはミリボルト)なのかは標準規格はありますが、実際には機器によって異なることがあり明示はできませんが、技術の詳細を知らない人でも適切なセットアップを行う方法はあります。
アナログ機器側で最大音量の出力を行います。デシベル表示があるボリュームならゼロデシベル(0dB)にします。通常これはボリュームを回し切ることになるでしょう。デシベル表示がない場合は最大80%程度にして最終的な調整を行います。
-

平均音量の大きな楽曲(J-POP等)を再生し、その最も騒々しい部分でデジタル機器(チャンネルデバイダー)のピークメーターがどうなるかを観察します。折々にクリップレベルになり、まれにピークレベルになるように最終的にアナログ機器側のボリュームを調整します。デジタル機器のピークメーターはアナログ機器よりずっとレベル表示が正確です。
ゼロデシベル入力を行ってもクリップレベルの入力にならない場合があるでしょう。その場合は [チャレンジ2ch 3-way] セクションの「SRC2496等セットアップ」ページを参考にしてください。
でも、最大音量のままチャンネルデバイダーの出力をパワーアンプに入力すれば大騒動になるのは確実です。デジタル機器を利用するマルチアンプシステムでマスターボリュームがとても重要であることがこれで分かります。つまり、システム全体の音量調整はチャンネルデバイダーの後段に設置したマスターボリュームで行いましょう。
| ホンの基礎知識 | |
| Copyright(C) 2018-2025 S&G Hermitage. All rights reserved. | |